 防犯スペシャリスト「守」
防犯スペシャリスト「守」はじめまして。「じぶん防犯」代表で、防犯設備士の守(まもる)と申します。
私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連企業で家庭用から業務用まで、数多くの防犯対策に従事してきました。
その経験を通じて、私が最も大切だと確信していることがあります。それは、本当の防犯とは、高価な最新機器を導入することだけで完結するものではない、ということです。
真の安全は、家族一人ひとりが「じぶんの身は、じぶんで守る」という意識を持つこと、つまり「じぶん防犯」の文化を家庭内に育むことから始まります。
防犯は、誰か一人が頑張るものではなく、子どもからおじいちゃん、おばあちゃんまで、家族全員がチームとなって取り組むべき課題なのです。
この考えは、決して精神論ではありません。警察庁の統計によれば、令和6年(2024年)の住宅を対象とした侵入窃盗の認知件数は1万6,000件にものぼります。
住宅対象侵入窃盗は、平成16年から概ね減少傾向にあり、令和6年は1万6,000件で前年比-8.4%と減少しています。それでも一日当たり約44件の侵入窃盗が発生しており、未だ多くの住宅が被害に遭っているのです。
引用:警察庁 住まいる110番 侵入窃盗データ
この数字を前にして、



「うちは大丈夫」
という油断は最も大きなリスクとなります。
しかし、絶望する必要はまったくありません。なぜなら、侵入窃盗犯が住宅に侵入する最も多い手口は、驚くべきことに「無締り」、つまり鍵のかかっていないドアや窓からの侵入だからです 。
これは、私たちのほんの少しの心掛け、日々の基本的な習慣がいかに強力な防犯対策になるかを物語っています。
この記事では、防犯のプロフェッショナルである私が、皆さまの家庭を安全な砦に変えるための具体的な方法を、余すところなくお伝えします。
まず、すべての土台となる「家族防犯会議」の開き方から始め、次に子どもと高齢の家族、それぞれの世代に合わせた具体的なルール作り、そして最後に、プロの視点から選んだ本当に効果のある防犯グッズとその活用法まで、包括的に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、皆さまの家庭には、単なるルールのリストではなく、家族全員で築き上げた「安全という名の絆」が生まれているはずです。
さあ、一緒に、あなたの大切な家族と住まいを守るための第一歩を踏み出しましょう。
すべての基本「家族防犯会議」を開こう
防犯対策を始めようと考えたとき、多くの方がまず防犯カメラや補助錠といった「モノ」に目を向けがちです。
しかし、私が最も重要だと考える最初のステップは、それではありません。すべての防犯対策の土台となる、絶対に欠かせないもの。それが「家族防犯会議」を開くことです。
この会議は、単に親が子どもにルールを言い渡す場ではありません。
家族全員が参加し、それぞれの立場から意見を出し合い、安全に対する共通の理解と責任感を育むための、非常に重要なプロセスです 。
なぜなら、一方的に押し付けられたルールは「やらされ仕事」になりがちですが、自分で作るプロセスに参加したルールは「自分たちの約束」として、主体的に守ろうという意識が芽生えるからです。
この会議のプロセスそのものが、家族の防犯意識を根付かせる最高のトレーニングになるのです。
では、どうすれば有意義な家族防犯会議を開けるのでしょうか。ここでは、その具体的な進め方をステップバイステップでご紹介します。
効果的な「家族防犯会議」の進め方
まず大切なのは、会議の雰囲気です。
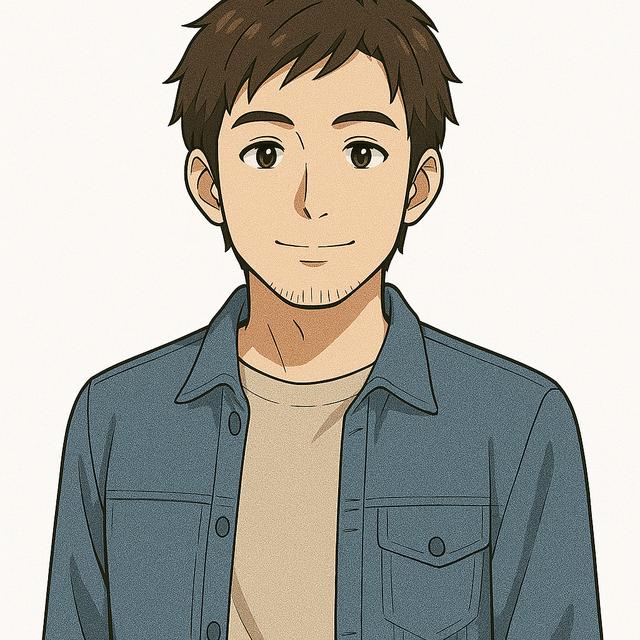
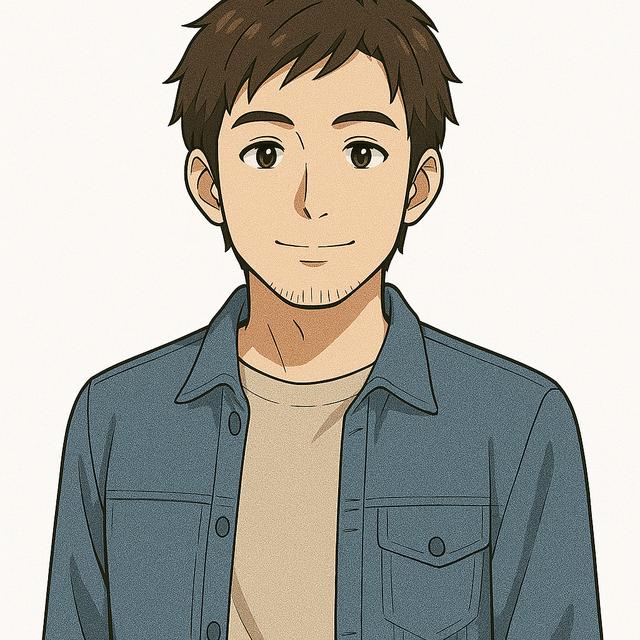
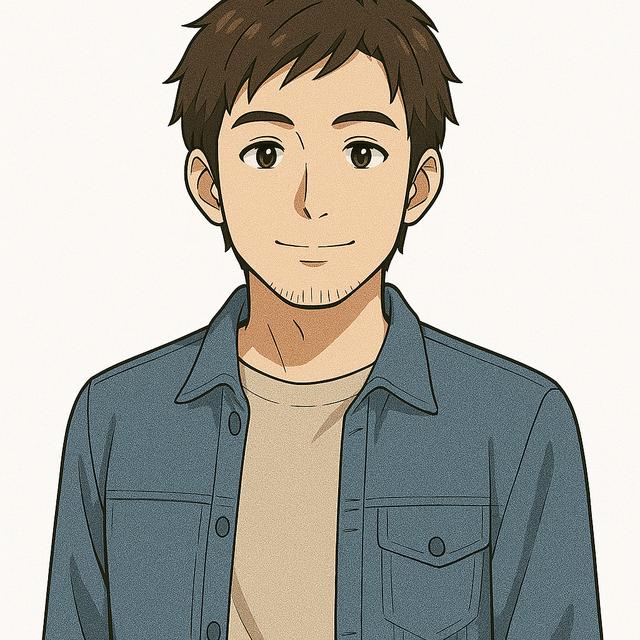
「これから怖い話をするぞ」
というような緊張感のあるものではなく、



「みんなが安心して楽しく暮らすために、家族チームで作戦会議をしよう!」
といった、前向きで協力的な雰囲気を作りましょう 。おやつを用意したり、リラックスできるリビングで行ったりするのも良い方法です。
会議がだらだらと長引かないよう、親が事前に話し合いたいテーマをいくつかリストアップしておくとスムーズです 。例えば、以下のようなテーマが考えられます。
- 知らない人が訪ねてきたときのルール
- 留守番をするときの約束事
- 「こども110番の家」など、いざというきの避難場所の確認
- 家族だけの「合言葉」を決める
- 災害時の連絡方法や集合場所
会議の主役は子どもたちでもあります。
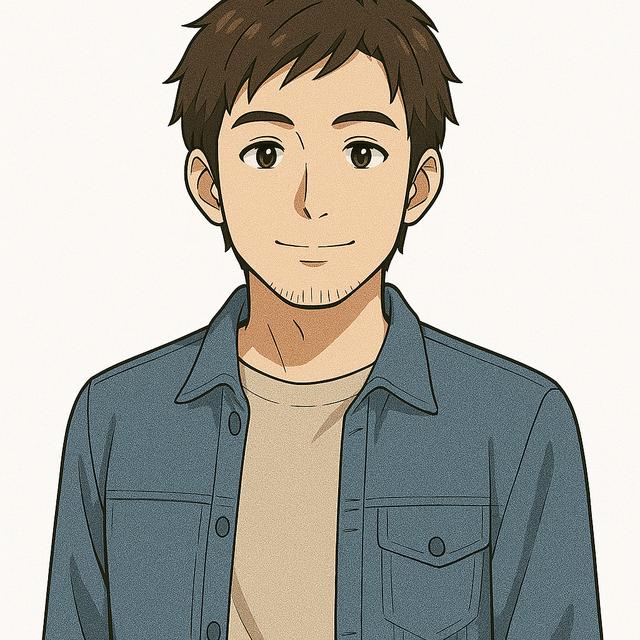
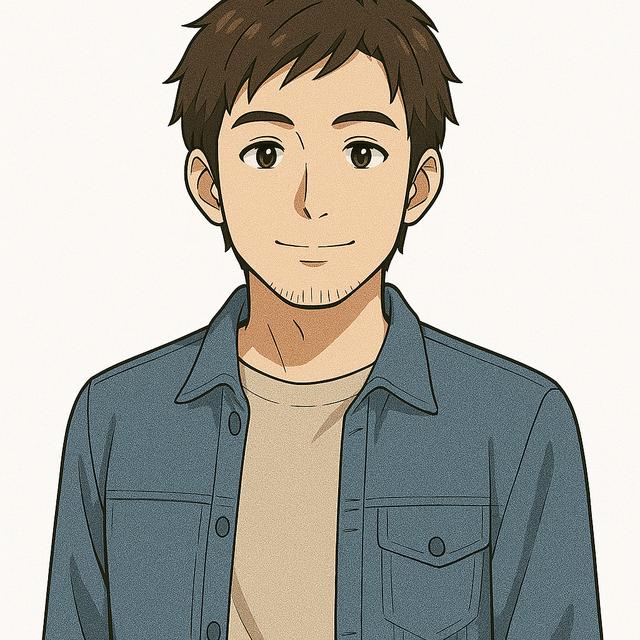
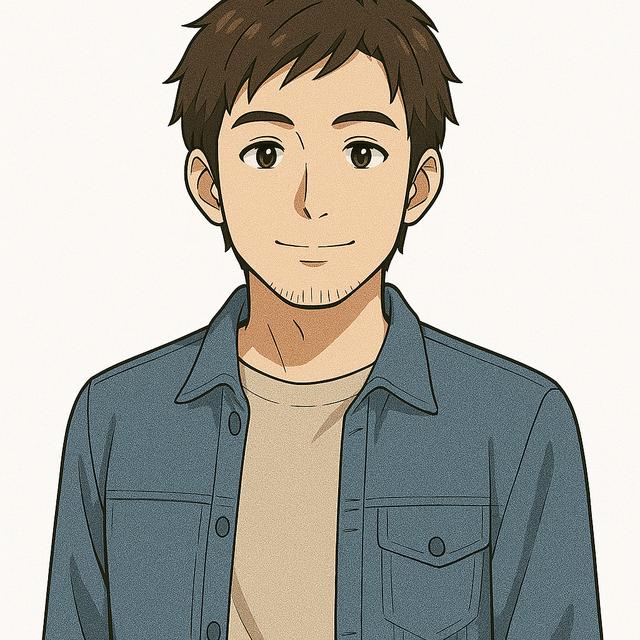
「どんなとき、怖いと感じる?」



「どういうルールがあったら安心するかな?」
など、具体的な質問を投げかけて、子ども自身の言葉で考えや気持ちを表現する機会を作りましょう 。
たとえそれが現実的でないアイデアだったとしても、まずはその気持ちを受け止めることが重要です。
会議では「どんな意見も否定しない」「相手の話は最後まで聞く」というグランドルールを設けましょう 。
特に子どもの話に対して、親が途中で
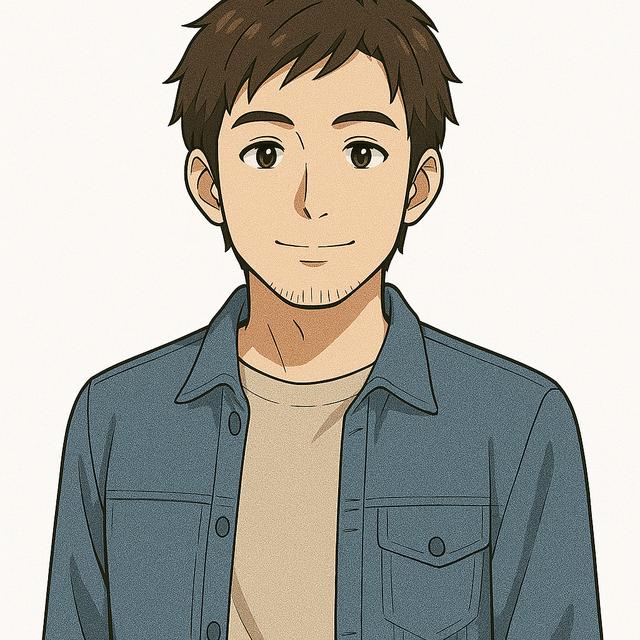
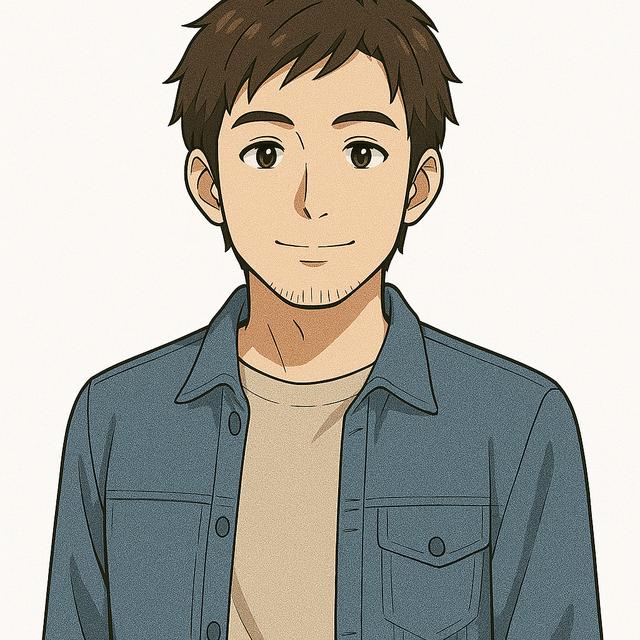
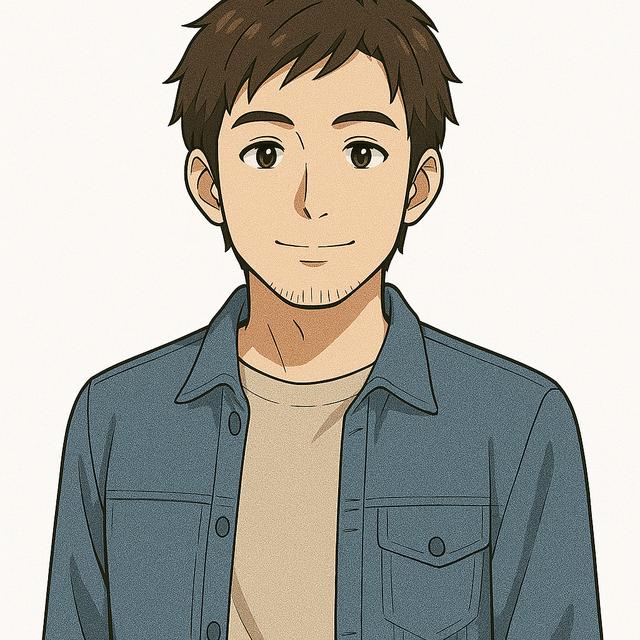
「それはダメ」



「そんなことあるわけない」
と遮ってしまうと、子どもは心を閉ざしてしまいます。そうなると、本当に危険な目に遭ったときでさえ、親に報告することをためらうようになってしまいかねません。
どんな意見でもまずは



「そう感じたんだね」「教えてくれてありがとう」
と受け止める姿勢が、信頼関係の土台となります。
会議で決まったルールは、その場で箇条書きにして、全員で確認しながら完成させます。
そして、完成した「わが家の防犯ルール」は、冷蔵庫やリビングの壁など、家族みんなが毎日目にする場所に貼り出しましょう 。
これにより、ルールが常に意識され、家族の共通認識として定着していきます。
家族の状況は常に変化します。子どもが成長すれば行動範囲も広がり、新たなリスクも生まれます。
ですから、家族防犯会議は一度きりで終わらせず、半年に一度や、新学期が始まるタイミングなど、定期的に開催することをお勧めします 。
ルールを現状に合わせてアップデートしていくことで、その実効性を保つことができます。
この「家族防犯会議」というプロセスを通じて、防犯は「面倒な制約」から「家族みんなで創り上げた大切な約束」へと変わります。
これこそが、あらゆる物理的な防犯設備よりも強力な、家庭内における究極のセキュリティシステムの第一歩なのです。
大切な子どもを守るための必須ルール
子どもたちの安全を守ることは、すべての親にとって最大の願いです。しかし、四六時中そばにいてあげることはできません。
だからこそ、子ども自身が危険を察知し、それを回避する力、すなわち「じぶんの身は、じぶんで守る」力を身につけさせることが不可欠です。
ここでは、子どもたちが直面する具体的なシチュエーションごとに、家庭で教えるべき必須のルールを詳しく解説します。
「外出時」「お留守番中」「デジタル世界」という3つの場面に分けて、具体的な行動レベルまで落とし込んだ約束事を一緒に学んでいきましょう。
外出時のルール:「じぶんの身は、じぶんで守る」を教える
子どもが一人で行動する時間が増えるにつれて、家の外でのリスクも高まります。
ここでは、子どもが覚えやすく、かつ実践的な防犯の知恵として、広く推奨されている「合言葉」を軸に、具体的なスキルを教えていきましょう。
覚えやすい「合言葉」をマスターする
まず、子どもに防犯の基本を教える上で非常に有効なのが、覚えやすい標語(合言葉)です。
これらは、いざという時にパニックになっても思い出せるよう、シンプルかつ行動に直結する言葉で作られています 。
| 合言葉 | 各文字の意味 | 具体的な行動 |
|---|---|---|
| いかのおすし | いか:知らない人についていかない | 声をかけられても、絶対について行ってはいけないと教えます。 |
| の:知らない人の車にのらない | 「乗せてあげる」と言われても、断固として断ることを徹底させます。 | |
| お:おおごえで助けを呼ぶ | 怖いと思ったら「助けて!」と叫び、防犯ブザーを鳴らします。 | |
| す:すぐに逃げる | その場からすぐに走り去り、大人がいる安全な場所へ向かいます。 | |
| し:周りの大人にしらせる | 逃げ込んだ先のお店の人や、近くにいる大人に何があったかを伝えます。 | |
| ひまわり | ひ:ひとりだけになる場所に行かない | 公園のトイレや誰もいない路地など、一人きりになる場所は避けます。 |
| ま:まわりから見えづらい場所に行かない | 高い塀や生い茂った草木で、外から見通しの悪い場所は危険です。 | |
| わ:わかれ道、わき道、裏道に気をつける | いつもと違う近道や暗い道は使わないようにします。 | |
| り:りようされていない場所に行かない | 使われていない空き家や、誰も遊んでいない公園には近づきません。 | |
| はちみつじまん | は:しつこくはなしかけてくる人 | 何度も話しかけてくる人は怪しいかもしれません。 |
| ち:ぐんぐんちかづいてくる人 | パーソナルスペースに急に入ってくる人は要注意です。 | |
| み:じっとみつめてくる人 | 何も言わずに、こちらをじっと見ている人には警戒します。 | |
| つ:あとをいつまでもついてくる人 | 後ろをつけられていると感じたら、すぐに逃げます。 | |
| じま:じっとまっている人 | 何をするでもなく、道の途中でじっと待っている人は不審です。 | |
| ん:「んっ?」とあやしい人 | これらに当てはまる「ん?」と感じる人には近づかないようにします。 |
これらの合言葉は、ただ暗記させるだけでなく、親子で一緒に散歩しながら



「『ひまわり』の『ま』は、ああいう場所のことだね」
というように、実際の景色と結びつけて教えることで、子どもの中に深く刻み込まれます 。


合言葉の先にある、実践的なスキル
合言葉は強力なツールですが、それだけでは不十分な場面もあります。より具体的な状況に対応するためのスキルを身につけさせましょう。
- 「知らない人」の本当の意味を教える
-
子どもは「知らない人=怖い顔をした人」と想像しがちですが、犯罪者は優しそうな顔で近づいてきます 。ですから、「知らない人についていかない」というルールは、より具体的にする必要があります。
私が推奨するのは、「お父さんやお母さんから、事前に直接『この人が迎えに行くからね』と聞いていない限り、たとえ知っている人でも、絶対について行ってはいけない。もし誰かが『お母さんに頼まれた』と言ってきたら、必ず家族で決めた『合言葉』で確認する」というルールです 。
これにより、子どもは相手の見た目や態度で判断するという難しいタスクから解放され、「事前に聞いていたか、合言葉を言えるか」というシンプルなYES/NOで行動できるようになります。
- 危険を感じたときの正しい行動
-
もし怖いと感じたら、



「失礼かな?」
などと考える必要は一切なく、すぐにその場を離れることが最優先だと教えます。
そして、叫ぶときは「キャー!」という悲鳴ではなく、「助けて!」と、はっきりと助けを求める言葉で叫ぶことが重要です。
悲鳴は遊び声と間違われる可能性がありますが、「助けて!」は緊急事態であることを周囲に明確に伝えます 。親子で声を出す練習をしておくのも効果的です。 - 防犯ブザーの正しい使い方
-
防犯ブザーは、ただ持たせるだけでは意味がありません。月に一度は親子で鳴らし、電池が切れていないか、子どもがためらわずにピンを抜けるかを確認しましょう 。
そして、万が一の時の最も効果的な使い方は、ピンを抜いてブザーを鳴らした後、自分とは逆の方向にブザーを投げ捨てることです 。
犯人は、音を止めようとしてブザーを拾うか、鳴り響く音の中であなたを追いかけるかの選択を迫られます。この一瞬の隙が、逃げるための貴重な時間を生み出すのです。 - 地域の「安全な避難場所」を知っておく
-
危険を感じたときに逃げ込める場所を、具体的に知っておくことは非常に重要です。
親子で一緒に通学路やよく遊ぶ公園の周りを歩き、「こども110番の家」のステッカーが貼ってある家やお店、交番、コンビニエンスストアなど、

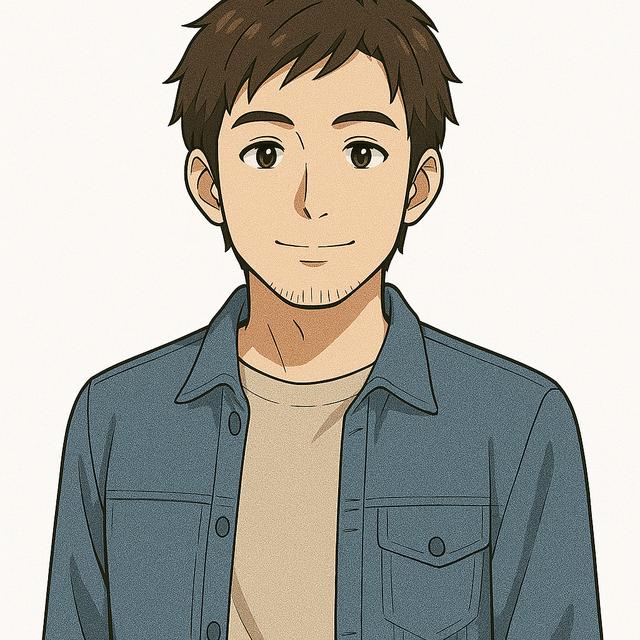
「いざという時はここに駆け込んでいいんだよ」
と具体的に教えておきましょう 。
お留守番のルール:家の中の安全を守る
子どもが一人で留守番をする機会は、成長とともに増えていきます。
家の中は安全な場所であるべきですが、そこには外とは異なる種類のリスクが潜んでいます。
ここでは、留守番中の子どもを犯罪や事故から守るためのルールを徹底解説します。
帰宅から留守番開始までの「安全儀式」
警備会社ALSOKが提唱する「いいゆだな」は、子どもが一人で帰宅する際の安全確認のポイントをまとめた、非常に優れた合言葉です 。これを毎日の「安全儀式」として習慣づけましょう。
- い:いえのカギを見せない(家の鍵は、家に着くまでカバンの中から出さない)
- い:いえのまわりをよく見る(家の近くに隠れている人や、ついてくる人がいないか確認する)
- ゆ:ゆうびんポストをチェックする(郵便物で溢れていると、留守だと知られてしまう)
- だ:だれもいなくても「ただいま!」と声を出す(中に人がいるように見せかける)
- な:なかに入ってすぐ戸じまりをする(玄関だけでなく、家中の窓の鍵も確認する)
引用:ALSOK公式サイト いいゆだな
この一連の動作を、子どもが自然にできるようになるまで、一緒に練習することが大切です。
訪問者対応の絶対的ルール
留守番中の訪問者対応には、たった一つ、絶対的なルールがあります。それは「予定にない訪問者には、絶対にドアを開けない」ということです 。
相手が宅配業者やガスの点検員、警察官を名乗ったとしても、事前に親から聞かされていなければ応対する必要はありません。
- インターホン・電話のルール
-
ドアと同様に、応答しないのが基本です。子どもの声が聞こえるだけで、大人不在のサインになってしまいます 。本当に重要な用件であれば、親の携帯電話に連絡が来るか、宅配便なら不在票が入ります。
「インターホンが鳴っても、電話が鳴っても、お父さんかお母さんが帰ってくるまで触らない」と、シンプルで明確なルールを決めましょう。
親子で「もし宅配便の人が来たらどうする?」といったロールプレイングをしておくと、子どもも落ち着いて対応できます 。
家の中で万が一の事態が起きたら(不審者が侵入してきた場合)
最も大切なのは、子どもの命です。物音に気づいても、絶対に犯人と対峙してはいけません。教えるべき行動は二つだけです。
「安全な逃げ道があれば、静かに逃げる」「逃げられなければ、クローゼットやベッドの下など、音を立てずに隠れる」。そして、安全が確保できてから警察や親に連絡します。家の財産よりも、自分の命が最優先であることを、繰り返し伝えましょう 。
デジタル世界のルール:見えない危険から守る
現代の子どもたちにとっての「玄関」は、物理的なドアだけではありません。
スマートフォン、タブレット、ゲーム機といったデジタルデバイスもまた、外部の危険が入り込んでくる新たな「玄関」となっています。
物理的な安全対策と同じくらい、デジタル世界の安全対策も重要です。
個人情報を守るためのルール
ネット上での出会いは、現実世界での出会い以上に慎重になる必要があります。子どもには、個人情報を守るための「デジタルの約束事」を明確に教えましょう。
- ネットの「3つの絶対ダメ」
-
- 本名、住所、学校名、電話番号などの個人情報は絶対に教えない。
- 自分の顔や家の周りがわかる写真は絶対に送らない。
- ネットだけで知り合った人とは絶対に会わない。
- 「なんか変だな?」は、すぐ相談のサイン
-
最も大切なのは、子どもがネット上で少しでも「怖い」「気持ち悪い」「変だな」と感じたときに、ペナルティを恐れることなく、すぐに親に相談できる関係を築いておくことです 。
そのためには、日頃から子どものネット利用に関心を持ち、

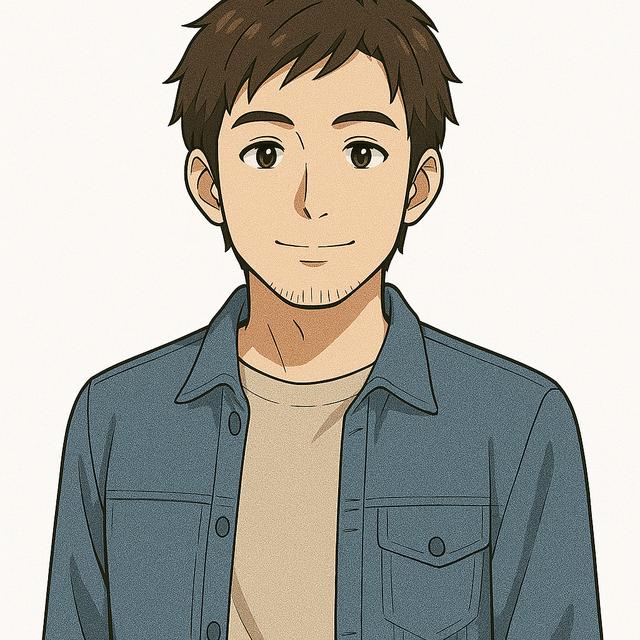
「どんなゲームが流行ってるの?」「面白い動画あった?」
など、オープンに会話できる雰囲気を作っておくことが重要です。
家庭の安全を考えるとき、私たちはつい空き巣や不審者といった物理的な脅威にばかり目を向けがちです。
しかし、統計や事例を見てみると、子どもたちにとっての危険は、家庭内の事故やデジタル空間にも数多く潜んでいます。
真の専門家としてのアドバイスは、これら3つの領域(物理的、偶発的、デジタル)をすべて網羅した、包括的な安全計画を立てることです。これらはすべて、重要な「家族の防犯ルール」なのです。
大切な高齢の家族を現代の脅威から守る
家族の安全を考えるとき、子どもたちと同様に、あるいはそれ以上に配慮が必要なのが、高齢の親や祖父母の存在です。
加齢に伴う身体的な変化や、情報社会への対応の難しさなど、高齢者特有の脆弱性を狙った犯罪は後を絶ちません。
ここでは、巧妙化する詐欺の手口から大切な家族を守るための「コミュニケーションの壁」の築き方と、日々の暮らしを安心して送るための「物理的な砦」の作り方について、具体的に解説していきます。
巧妙化する詐欺から守る:「合言葉」とコミュニケーション
高齢者を狙う詐欺犯は、人の善意や不安、孤独感につけ込むプロフェッショナルです。
彼らは巧みな話術でパニック状態を作り出し、冷静な判断力を奪います 。まずは、敵の手口を知ることから始めましょう。
代表的な詐欺の手口
- 還付金詐欺
-
市役所や税務署の職員を名乗り、
「医療費や税金の還付金があります」
と電話をかけてきます。そして
「手続きのためにATMへ行ってください」
と誘導し、巧みな指示で犯人の口座にお金を振り込ませる手口です 。公的機関がATMでの手続きを指示することは絶対にありません。
- オレオレ詐欺
-
息子や孫になりすまし、


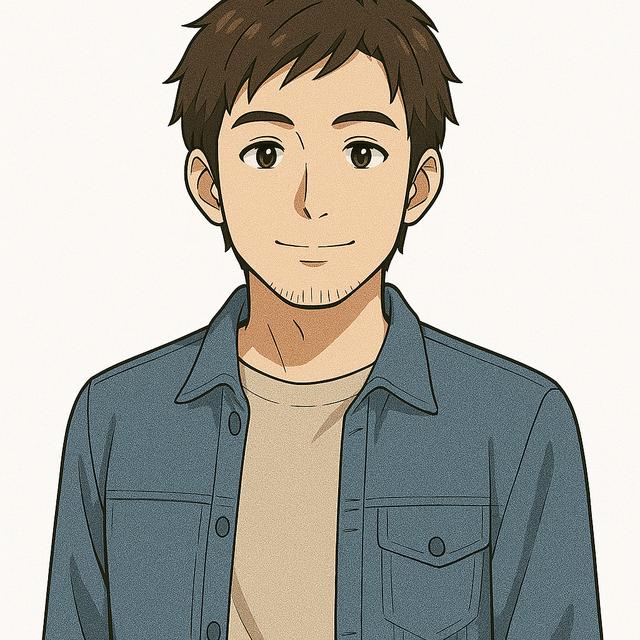
「会社のお金を使い込んだ」「事故を起こして示談金が必要だ」
などと、緊急事態を装って動揺を誘い、お金を要求します 。
- 架空請求詐欺
-
SMSやハガキで
「有料サイトの未納料金があります。支払わなければ法的措置をとります」
などと脅し、不安を煽って連絡させ、電子マネーなどで支払いを要求する手口です 。
- 劇場型詐欺
-
子、警察官、弁護士など、複数の犯人が次々と登場し、手の込んだストーリーで信じ込ませる悪質な手口です。
「あなたの名義が不正に使われている」「名義貸しは犯罪だ」
などと言って恐怖心を煽り、解決金名目でお金をだまし取ります 。
最強の防御壁は「コミュニケーション」
これらの巧妙な詐欺に対抗する最も強力な武器は、ハイテクな機器ではなく、家族の「コミュニケーション」です。
- 絶対的な黄金ルール
-
家族で「電話でお金の話が出たら、どんな理由であれ、一度電話を切って、必ず家族に相談する」というルールを徹底しましょう 。このワンクッションが、犯人が作り出す「今すぐ払わないと大変なことになる」という焦りの呪縛を解く鍵となります。
- 家族だけの「合言葉」を決める



「うちのペットの名前は?」「中学生の時の部活は何だった?」
など、家族しか知らない質問と答えを「合言葉」として決めておきます 。お金を要求する不審な電話がかかってきたら、まずこの合言葉を尋ねるように、親御さんと約束しておきましょう。
- 定期的な連絡が最大の抑止力
-
特別な用事がなくても、こまめに電話や顔を合わせることが、何よりの防犯になります。


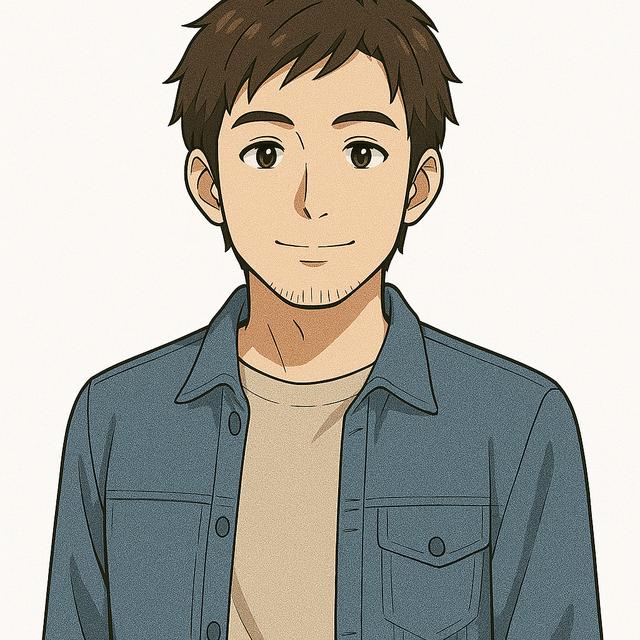
「変わりない?」「最近、こんな詐欺が流行っているらしいよ」
といった何気ない会話が、親御さんの孤立感を和らげ、詐欺犯がつけ入る隙をなくします 。
- 防犯機能付き電話機の活用
-
迷惑電話防止機能が付いた電話機を導入するのも非常に有効です。知らない番号からの電話を拒否したり、通話内容を自動で録音する機能は、犯人にとって大きな脅威となります。
また、常に留守番電話設定にしておき、相手を確認してからかけ直す習慣をつけるだけでも、犯人と直接話すリスクを大幅に減らせます 。
シニアの住まいを安全な砦に
高齢になると、とっさの判断力や身体的な対応能力が低下することがあります。
そのため、犯罪者と万が一にも鉢合わせしないよう、侵入を未然に防ぐ「予防」が何よりも重要になります 。
物理的な防犯対策の強化
- 玄関と窓の守りを固める
-
- 鍵:ピッキングに強いディンプルキーなど、防犯性の高い鍵に交換し、玄関ドアには必ず補助錠を取り付けて「1ドア2ロック」を徹底します 。
- 窓:窓にも補助錠を取り付け、防犯フィルムを貼ることでガラス破りを防ぎます。特に1階の窓や、ベランダに面した窓には、可能であれば面格子を設置するとさらに安心です 。
あわせて読みたい
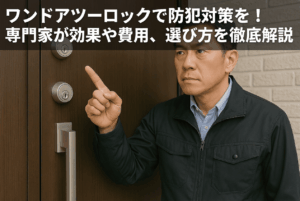 ワンドアツーロックで防犯対策を!専門家が効果や費用、選び方を徹底解説 はじめまして。「じぶん防犯」代表、防犯設備士の守(まもる)と申します。 私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連企業で家庭用から業務用まで、数多くの防犯…
ワンドアツーロックで防犯対策を!専門家が効果や費用、選び方を徹底解説 はじめまして。「じぶん防犯」代表、防犯設備士の守(まもる)と申します。 私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連企業で家庭用から業務用まで、数多くの防犯… - 光と環境で侵入を諦めさせる
-
- センサーライト:玄関や勝手口、庭の暗がりなど、侵入経路になりそうな場所にセンサーライトを設置します。突然の光は侵入者を驚かせ、人目を引くことを嫌う犯行を諦めさせる効果があります。また、夜間の転倒防止にも役立ちます 。
- 見通しの確保:庭の植木は低めに剪定し、家の周りの見通しを良くしましょう。エアコンの室外機や物置、ゴミ箱などが2階への足場にならないよう、設置場所にも注意が必要です 。
離れて暮らす家族のためのテクノロジー
遠方で暮らす親御さんが心配な場合は、現代のテクノロジーが大きな助けとなります。
ただし、ここで重要なのは、セキュリティとプライバシー、そして使いやすさのバランスです。
高齢の親御さんにとって、操作が複雑だったり、常に監視されているように感じたりするシステムは、かえってストレスになり、使われなくなってしまいます。
大切なのは、本人の生活に溶け込み、負担にならない方法を選ぶことです。
- モニター付きインターホン
-
ドアを開けずに訪問者の顔を確認できるこの設備は、高齢者世帯の必須アイテムです。不要なセールスや不審者を、安全な室内から撃退できます 。
- 見守りサービス
-
セキュリティ会社が提供する見守りサービスは、防犯と安否確認の両面で心強い味方です。
- センサー型:冷蔵庫の開閉や室内の人の動きをセンサーで感知し、一定時間動きがないなど、異常があった場合に家族へ通知するサービスです。カメラを使わないため、プライバシーへの抵抗感が少なく、受け入れられやすいのが特徴です 。
- カメラ型:室内の様子を映像で確認できるため安心感は高いですが、導入にはプライバシーへの配慮から、必ず本人の同意を得ることが不可欠です 。
- 緊急通報システム:体調が急変したときや転倒したときに、ペンダント型のボタン一つで警備会社に通報できるサービスです。
セコムやALSOKなどが提供しており、警備員が駆けつけてくれるため、万が一の際の安心感が格段に高まります 。火災やガス漏れの監視機能を追加できる場合も多く、総合的な安全確保に繋がります 。
高齢の家族を守るための防犯対策は、「過保護」や「干渉」ではありません。
それは、変化していく心身の状態に寄り添い、尊厳を守りながら、安心して自立した生活を続けてもらうための、家族からの愛情表現なのです。
空き巣に「狙われない家」をつくる
これまで、家族一人ひとりの「ソフト面」での防犯ルールについてお話してきましたが、ここでは住まいそのものを守る「ハード面」の対策、つまり物理的なセキュリティについて詳しく解説します。
防犯対策の極意は、泥棒の心理を理解し、



「この家は面倒くさそうだ」「リスクが高い」
と思わせて、標的から外させることにあります。
完璧な要塞を築く必要はありません。近隣の家よりも「少しだけ侵入しにくい家」にするだけで、狙われる確率は劇的に下がるのです。
泥棒の心理を読み解く:侵入犯が嫌う家とは
プロの侵入犯は、犯行前に必ず下見をすると言われています。彼らは、最小限のリスクで、短時間のうちに目的を達成できる家を探しています。
つまり、彼らが「嫌う家」の条件を知ることが、最も効果的な防犯対策の第一歩となります。
- 侵入犯は「楽な道」を選ぶ
-
何度もお伝えしている通り、住宅への侵入窃盗で最も多い手口は「無締り」、つまり鍵のかかっていない玄関や窓からの侵入です 。
これは、侵入犯が高度な技術を持つ怪盗ではなく、単に楽な機会をうかがう日和見主義者であることを示しています。日々の施錠習慣こそが、最強の防御なのです。 - 「5分」の壁
-
侵入犯が最も恐れるのは「時間」と「人目」です。警察庁の調査によれば、侵入に5分以上かかると判断した場合、約7割の侵入犯が犯行を諦めるというデータがあります 。(出典:警察庁 住まいる110番 5分が分かれ目)
物理的な防犯設備の目的は、この「5分」という時間を稼ぎ出し、犯行を断念させることにあります。 - 侵入犯が下見でチェックするポイント
-
- 侵入のしやすさ:鍵が開いている場所はないか、足場になるものはないか、身を隠せる植え込みや暗がりはないか 。
- 留守のサイン:郵便受けが新聞やチラシでいっぱい、夜になっても家が真っ暗、洗濯物が干しっぱなし 。
- 防犯意識の低さ:防犯カメラやセンサーライトが見当たらない、警備会社のステッカーが貼られていない、窓に補助錠がない。
これらのポイントを潰していくことが、「狙われない家」作りの基本戦略となります
| 順位 | 侵入手口 | 割合(令和6年 住宅対象侵入窃盗) |
|---|---|---|
| 1位 | 無締り | 47.6% |
| 2位 | ガラス破り | 35.7% |
| 3位 | 不明 | 6.1% |
| 4位 | その他 | 3.0% |
この表が示す通り、対策の優先順位は明らかです。まず「施錠の徹底」、次に「窓の強化」。
この2つに取り組むだけで、侵入窃盗の約4分の3を占める手口に対応できるのです。
防犯のプロが教える最強の住宅セキュリティ製品ガイド
では、具体的にどのような製品を、どのように組み合わせれば効果的なのでしょうか。
ここでは「防御の層」という考え方に基づき、多重の防御壁を築くための製品ガイドをご紹介します。
一つの対策に頼るのではなく、複数の対策を重ねることで、相乗効果が生まれ、より強固なセキュリティが実現します。
ドア・窓の物理的強化
侵入犯が最初に接触する、最も重要な防御ラインです。
- 補助錠(ワンドアツーロック)
-
玄関ドアに鍵が一つしかない場合は、必ず補助錠を取り付け「ワンドアツーロック」にしましょう 。補助錠の最大の効果は、外から見て「この家は防犯意識が高い」とアピールする視覚的な抑止力と、解錠にかかる時間を倍増させることにあります 。
賃貸物件でも、ドアに穴を開けずに設置できるタイプがあります 。 窓にも、安価で取り付けが簡単なサッシ用の補助錠が非常に有効です。クレセント錠(半月型の鍵)を破られても、補助錠がストッパーとなり、窓が開くのを防ぎます 。 - 防犯フィルム
-
侵入手口の第2位である「ガラス破り」への最もコストパフォーマンスの高い対策が、防犯フィルムです 。ガラス自体を交換するよりも手軽に窓を強化できます。
- 効果の仕組み:フィルムが割れたガラスを強力に保持し、人が通れるほどの穴を開けるのに大きな音と時間(5分以上)をかけさせ、侵入を断念させます 。
- 製品の選び方:必ず「CPマーク」付きの製品を選んでください。これは、警察庁などが定めた厳しい基準をクリアし、「5分以上の侵入抵抗性能」が保証された製品の証です 。
- 施工の最重要注意点:防犯フィルムは、必ず窓ガラス全面に貼る(全面貼り)必要があります。鍵の周りだけに貼る「部分貼り」は、プロの侵入犯にとっては全く意味がありません。
彼らはフィルムの貼られていない部分を割り、フィルムごとガラスを外してしまうからです 。また、フィルムとガラスの間に気泡やホコリが入ると強度が著しく低下するため、効果を最大限に引き出すには、専門業者による施工を強くお勧めします 。
あわせて読みたい
 CPマークとは?【防犯専門家が徹底解説】空き巣が嫌がる「5分」の秘密と、安心できる製品の選び方 はじめに:なぜ今、防犯対策が重要なのか はじめまして。「じぶん防犯」代表、防犯設備士の守(まもる)と申します。私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連の…
CPマークとは?【防犯専門家が徹底解説】空き巣が嫌がる「5分」の秘密と、安心できる製品の選び方 はじめに:なぜ今、防犯対策が重要なのか はじめまして。「じぶん防犯」代表、防犯設備士の守(まもる)と申します。私はこれまで10年以上にわたり、セキュリティ関連の…
光・音による心理的抑止
侵入犯の「人目につきたくない」という心理を逆手に取った、効果的な防御層です。
- センサーライト
-
暗闇は侵入犯の最大の味方です。センサーライトは、その味方を奪う最も強力な武器の一つです 。
- 設置場所:玄関、勝手口、ガレージ、庭に面した大きな窓の下など、侵入経路となりうる場所や死角に設置します。簡単に手が届かない高さに取り付けるのがポイントです 。
- 選び方のコツ:道路を通る車や風で揺れる木々に反応して、近所の迷惑にならないよう、センサーの感度や向きを調整できるモデルを選びましょう 。電源工事が不要なソーラー充電式のLEDタイプは、手軽で維持費もかからずお勧めです 。
- 設置場所:玄関、勝手口、ガレージ、庭に面した大きな窓の下など、侵入経路となりうる場所や死角に設置します。簡単に手が届かない高さに取り付けるのがポイントです 。
- 防犯ブザー(窓用アラーム)
-
窓の振動や開閉を検知して大音量のアラームを鳴らす製品です。突然鳴り響く100デシベル以上の警告音は、犯人を強烈に威嚇し、犯行を中断させる効果が期待できます 。これも安価で設置が簡単な、優れた追加対策です。
映像による威嚇と証拠確保
最終的な防御層として、侵入をためらわせ、万が一の際の証拠を残すための設備です。
- モニター付きインターホン
-
もはや現代住宅の標準装備と言える防犯設備です。訪問販売や点検を装う手口に対して、ドアを開けることなく相手を確認し、対応を判断できるため、多くの犯罪を未然に防ぐことができます 。
【選ぶべき機能】
- 広角レンズ:カメラの死角に隠れる人物も映し出すため 。
- 録画機能:留守中の訪問者も記録し、不審者の下見の証拠にもなるため 。
- 夜間用LEDライト:夜でも鮮明に顔を確認するため 。
- スマートフォン連携:外出先からでも来客対応ができ、留守を悟らせないため 。
- 防犯カメラ
-
究極の視覚的抑止力です。カメラが設置されているという事実だけで、侵入犯はその家をターゲットから外す可能性が高まります 。ダミーカメラはプロに見破られることが多いため、実際に録画機能のある本物のカメラを設置することをお勧めします 。
このように、複数の防御策を重ね合わせる「多層防御」の考え方が、あなたの家を「侵入しにくい、リスクの高い家」へと変貌させます。
一つの鍵が破られても、次の防御壁が待ち受けている。この積み重ねが、侵入犯の心を折るのです。
結論:継続的な「じぶん防犯」で、家族に本当の安心を
ここまで、家族で取り組む防犯ルールについて、子どもから高齢者、そして住まいそのものに至るまで、包括的にお話してきました。
最後に、防犯スペシャリストとして、皆さまに最もお伝えしたいメッセージを改めて強調させてください。
それは、「防犯とは、一度買ったら終わる製品ではなく、家族で育み続ける習慣である」ということです。
この記事でご紹介した数々のルールや製品は、あくまで道具にすぎません。
その道具を本当に意味のあるものにするのは、家族一人ひとりの「じぶん防犯」への意識と、日々の継続的な取り組みです。
私たちの目指すべき「本当の安心」は、以下の3つの柱によって支えられています。
- コミュニケーションの柱:すべての基本は、家族の対話です。「家族防犯会議」を定期的に開き、日頃から何でも話し合える関係を築くこと。これが、どんな高価なセキュリティシステムよりも強力な、家族を守るための基盤となります。
- 習慣の柱:玄関や窓の施錠を徹底する。帰宅時間を伝え合う。お互いの様子に気を配る。こうした地道な習慣の積み重ねが、犯罪者がつけ入る隙をなくし、最も効果的な防御壁を築き上げます。
- 多層防御の柱:住まいのセキュリティは、一つの対策に頼るのではなく、物理的な強化(鍵、フィルム)と心理的な抑止(光、音、映像)を賢く組み合わせることで、その効果が何倍にも高まります。侵入犯に「面倒だ」と思わせる、賢い層の構築が重要です。
防犯について考えることは、決して家族を恐怖で縛り付けることではありません。
むしろ、それは危険を正しく理解し、備えることで、不必要な不安から解放され、心から安心して日々の生活を送るための、積極的で前向きな営みなのです。
この記事が、皆さまの家庭にとって、安全で安心な毎日を築くための一助となれば、私にとってこれ以上の喜びはありません。
今日から、あなたの家族という最高のチームで、「じぶん防犯」を始めてみてください。その一歩一歩が、何物にも代えがたい、家族の笑顔と平和な暮らしを守ることに繋がっていくはずです。




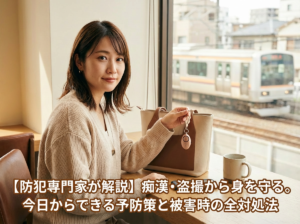
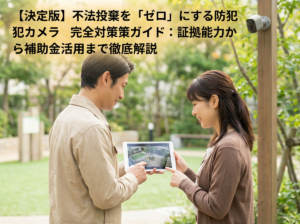



コメント