はじめに:お子様を危険から守るために、今できること
じぶん防犯代表、防犯設備士の守(まもる)です。セキュリティ関連企業に10年以上勤務、家庭用・業務用を問わず数多くの防犯対策案件に携わってきました。
私自身も一人の父親として、お子様を思う親御さんのご心配は痛いほどよく分かります。日々報じられる子どもが巻き込まれる事件に、胸を痛めている方も少なくないでしょう。
本記事の目的は、いたずらに不安を煽ることではありません。むしろ、正しい知識を身につけることで、漠然とした不安を「具体的な対策」に変え、自信を持って日々を過ごしていただくことです。
真の安心は、恐怖からではなく、準備から生まれます。
子どもを取り巻く危険は、かつての「知らない人についていかない」という単純な注意喚起だけでは防ぎきれないほど多様化しています。
デジタル社会の進展に伴うSNSのリスク、便利な育児グッズに潜む思わぬ事故、そして公園などでの親同士の些細なトラブル。これらすべてが、お子様の安全を脅かす要因となり得ます。
そして、最も重要な事実の一つは、子どもを狙った犯罪の多くが、非日常的な場所ではなく、私たちのありふれた日常空間で発生しているという点です。
警察の統計データは、その現実を明確に示しています 。例えば、13歳未満の子どもが被害に遭う場所として最も多いのは、決して暗い路地裏だけではありません。
「道路上」や「公園」、そして「住宅」といった、ごく身近な場所なのです。特に小学生が被害に遭う時間帯は「平日の帰宅後」が突出して多い状況です。
小学生は16時をピークとして15時台から17時台
引用:警視庁 警視庁子ども・女性の安全対策に関する有識者研究会提言書」について
これは、安全なはずの「家」から、もう一つの安全なはずの「公園」や「スーパー」へ移動する、その「道のり」こそが、最も警戒すべき時間帯であることを示唆しています。
本稿では、子育て中の母親が直面する具体的なシチュエーション、すなわち「ベビーカーでの移動」と「公園での過ごし方」に焦点を当てながら、日常に潜むリスクを体系的に解説し、今日から実践できる具体的な防犯対策を網羅的にお伝えします。
| 項目 | 詳細 |
| 主な被害罪種(13歳未満) | 略取誘拐が最も高い割合を占め、令和2年中の統計では認知件数337件中114件(33.8%)に上る。暴行、傷害、強制わいせつなども発生。 |
| 主な発生場所(13歳未満) | 住宅(478件)、道路上(355件)、公園等(161件)、商業施設(98件)など、日常生活の場が中心。 (※ 平成24年から平成28年までに警視庁で認知した件数による) |
| 主な発生時間帯(小学生) | 「平日の帰宅後」が131件と最も多く、全体の33.9%を占める。 |
引用:警視庁 警視庁子ども・女性の安全対策に関する有識者研究会提言書」について
ベビーカーでのお出かけ:移動中と外出先の防犯対策
ベビーカーでのお出かけは、子育て中の母親にとって日常的な行動です。
しかし、この何気ない移動時間には、事故や犯罪のリスクが数多く潜んでいます。
ここでは、家を出てから帰宅するまでの一連の流れを「一つの旅」と捉え、各段階で必要となる防犯・安全対策を専門家の視点から徹底的に解説します。
「ながらスマホ」の危険性:その一瞬の隙が命取りに
まず、最も基本的かつ重大な注意点からお話しなければなりません。それは「ながらスマホ」の危険性です。
スマートフォンに気を取られている保護者は、犯罪者にとって「格好のターゲット」です。それは、周囲への警戒心が著しく低下していることを自ら示しているに他なりません。
この危険性は、単に人や物にぶつかるといった物理的な事故に留まりません 。
人間の脳は、一つの作業に集中すると、他の情報を取りこぼしやすくなる状態に陥ります 。スマートフォン画面の小さな世界に没頭している間、あなたの視野は極端に狭まり、背後から近づく足音や、横から現れる不審な人物の気配を察知することはほぼ不可能です 。
これは、あなた自身がひったくりなどの被害に遭うリスクを高めるだけでなく、何よりも守るべきお子様を直接的な危険に晒す行為です。
保護者という「最後の砦」が機能不全に陥っている状態であり、その一瞬の隙を突いて子どもに危害を加えようとする者もいるのです。
横断歩道を渡るとき、人混みを歩くとき、駐車場を通るときなど、危ない場所ではスマートフォンを必ずカバンにしまいましょう。
歩きながらスマホを見ると、周りの様子に気づかず、事故にあったり、危険な人に気づけなかったりします。
どうしても連絡を確認したいときは、道の端などで立ち止まるのではなく、安全なお店の中や建物の中など、落ち着いて対応できる場所に移動してからにしてください。
これはマナーというよりも、あなた自身やお子さんの命を守るためにとても大切な行動です。ちょっとの注意が、大きな事故やトラブルを防ぎます。
ベビーカー自体の盗難を防ぐ4つの対策
高価なベビーカーは、転売目的で盗難の対象になることがあります。
特に、装飾が少なく持ち主を特定しにくいモデルは、犯人にとって売りさばきやすく、狙われやすい傾向にあります 。
ベビーカーの盗難防止は、単一の対策ではなく、複数の防御策を組み合わせる「多層防御」の考え方が極めて有効です。
抑止力(犯行意欲を削ぐ)
まず、あなたのベビーカーを
「盗んでも割に合わない」
と思わせることが重要です。
- 個性的な目印をつける
-
取り外しにくい、パーソナライズされたネームタグや、色鮮やかなハンドルカバー、特徴的なステッカーなどを付けましょう 。これにより、ベビーカーが「盗品」として目立ちやすくなり、転売が困難になるため、犯人はターゲットから外す可能性が高まります。
物理的防御(犯行を困難にする)
次に、物理的に盗めなくする対策を講じます。
- 施錠の徹底
-
短時間であっても、ベビーカーから目を離す際は必ずロックをかけましょう。自転車用のワイヤーロックやチェーンロックを使い、柱などの固定物にくくりつけるのが最も効果的です 。
テーマパークなど固定物への施錠が禁止されている場所では、ベビーカーの車輪同士をロックし、転がして持ち去れないようにするだけでも効果があります 。 - ロックの選び方
-
- ワイヤー/ケーブルロック: 軽量で扱いやすく、車輪をロックするのに適しています。
- チェーンロック: ワイヤーより頑丈ですが、重さがあります。
ダイヤル式 vs 鍵式: ダイヤル式は鍵を紛失する心配がなく便利ですが、鍵式の方が一般的にセキュリティは高いとされています。
警報(犯行を知らせる)
リスクが高い場所や、高価なベビーカーの場合は、さらに一歩進んだ対策を検討しましょう。
- 防犯ブザーの設置
-
自転車用に市販されている振動感知式のアラームが有効です。不正な動きを感知すると大音量で鳴り響き、犯人を驚かせ、周囲の注意を引くことができます 。
追跡(万が一の時の備え)
最後の砦として、盗難後の発見に繋げる対策です。
- GPSトラッカーの活用
-
AppleのAirTagのようなGPSトラッカーを、ベビーカーのシートの裏地など、外から見えない場所に忍ばせておくことで、万が一盗難に遭った際に位置情報を追跡し、発見に繋がる可能性を高めることができます 。
これらの4つの層を意識し、ご自身の状況やベビーカーの価格に応じて対策を組み合わせることで、より強固なセキュリティを構築できます。
迷子のリスク管理
スーパーやショッピングモールでの買い物は、保護者にとって「移動」「子どもの監督」「品選び」という複数のタスクを同時にこなす必要があるため、認知的な負荷が非常に高い状況です。
この「タスク過多」こそが、様々な危険の根本原因となります。
【迷子防止対策】
子どもが歩き始めると、迷子のリスクが急激に高まります。
- 服装の工夫
-
人混みの中でも目立つ、明るく派手な色の服を着せることで、万が一見失った際にも発見しやすくなります 。
- 事前の約束
-
入店前に
「お店の中では手をつなごうね」
「もしママが見えなくなったら、その場から動かないで『ママ!』って大きな声で呼ぶんだよ」といった具体的なルールを決めておきましょう 。
- 迷子防止グッズの活用
-
活発に動き回るお子様には、迷子防止ハーネスが有効です。また、GPS機能付きのキーホルダー(あんしんウォッチャーなど)やAirTagを持たせることも、万が一の際の強力な安全策となります 。
- 万が一の行動計画
-
もしお子様とはぐれてしまったら、パニックにならず、すぐに近くの店員に助けを求めてください。その日の朝、家を出る前に撮っておいたお子様の写真(服装がわかるもの)を提示すると、捜索がスムーズに進みます 。
これらの対策は、買い物の際の認知的な負荷を軽減し、保護者が最も重要な「子どもの監督」というタスクに集中できるようにするためのものです。
子どもの連れ去り防止:ベビーカーに乗っている時こそ注意
ベビーカーに乗っている子どもは、一見すると安全に見えます。しかし、防犯の観点からは「静止した、予測可能なターゲット」であり、セキュリティの焦点は子ども自身から、保護者の「状況認識能力」へと完全に移行します。
ベビーカーは一時的な物理的障壁にはなりますが、それを守る「防火壁」は保護者自身なのです。
- 誘導
-
子どもが自ら歩いてどこかへ行ってしまうリスクがない代わりに、犯罪者は子どもを誘い出す必要がありません。その代わり、保護者の注意を逸らすことに全力を注ぎます。
- 巧妙な手口
-
犯人は、物を落として拾わせる、道を聞くふりをする、赤ちゃんを褒めちぎるなど、ごく自然なやり方で保護者の注意を自分に引きつけ、その隙に犯行に及ぼうとします 。
- 安全な距離の確保
-
見知らぬ人が近づいてきたら、無意識に一歩下がる、ベビーカーを自分と相手の間に置くなど、物理的な距離を保つ習慣を身につけましょう。大人が腕を伸ばせば届く範囲は「危険領域」です。常にその外側にいることを意識してください 。
- ハーネスを防犯ツールとして活用
-
ベビーカーの5点式ハーネスは、転落防止だけでなく、強力な防犯ツールにもなります。複雑なバックルを外すのにかかる数秒が、犯人の「素早く連れ去る」という計画を頓挫させる可能性があるのです。子どもが自分で外しにくいように工夫された補助具も市販されています 。
- 絶対に目を離さない
「少しだけだから」
と車内に子どもを残してコンビニに入る、ガソリンスタンドで支払いのために背を向ける、といったほんの僅かな時間が、犯人にとっては十分な犯行時間となり得ます。
ベビーカーに乗っている時こそ、保護者の警戒心が子どもの安全に直結することを、決して忘れないでください。
公園に潜む危険:事故・不審者・親同士のトラブルから子どもを守る
公園は子どもたちにとって最高の遊び場ですが、その開放的な空間には、事故や犯罪、さらには人間関係のトラブルといった様々な危険が潜んでいます。
ここでは、公園という環境を専門家の視点で分解し、目に見えにくいリスクを可視化していきます。
まずは安全確認:危険な公園のチェックリスト
公園の安全性を評価する最も効果的な方法は、犯罪者の視点に立ってその場所を見ることです。
犯罪者は、犯行がしやすく、見つかりにくく、逃げやすい場所を好みます。
以下のチェックリストを使って、いつもの公園を「犯罪機会論(CPTED)」の観点から点検してみてください。
見通しの悪さ
生い茂った樹木や高いフェンス、トンネル状の滑り台など、道路やベンチから死角になる場所はありませんか? これらは、不審者が身を隠したり、人目につかずに子どもに接近したりするのに最適な場所です 。
複数の管理されていない出入り口
公園の出入り口が多ければ多いほど、犯人にとっては逃走経路が増えることになり、犯行に及びやすくなります。特に入り組んだ場所にある出入り口は要注意です 。
不適切なベンチの配置
道路に背を向けて設置されていたり、木陰の奥まった場所にあったりするベンチは、不審者が人目を気にせず子どもたちを物色するのに好都合です。彼らは、遊具で遊ぶ子どもたちを観察し、ターゲットを選定している可能性があります 。
孤立したトイレ
公園の隅に孤立して設置されたトイレは、子どもを連れ込むのに使われやすい非常に危険な場所です。また、トイレが汚れていたり、落書きが放置されていたりするのは、公園の管理が行き届いていない証拠。管理者の関心が低い場所は、犯罪が起きやすい環境と言えます 。
管理不足のサイン
壊れた遊具が放置されている、ゴミ箱が溢れている、落書きが多いといった状態は、「この場所は誰も気にかけていない」というメッセージを犯罪者に送ってしまいます(割れ窓理論)。このような場所では、規範意識が低下し、犯罪が起こりやすくなります 。
このチェックリストは、単に「危ない場所」を探すのではなく、「犯罪者に機会を与えてしまう環境」を見つけ出すためのツールです。この視点を持つことはとても重要です。
不審者の見分け方と対処法
犯罪者は「怪しい見た目」をしているとは限りません。むしろ、周囲に溶け込むためにごく普通の服装をしていることがほとんどです 。
重要なのは見た目ではなく、その場の状況にそぐわない「行動」に注目することです。
犯罪者は「怪しい見た目」をしているとは限りません。むしろ、周囲に溶け込むためにごく普通の服装をしていることがほとんどです 。
重要なのは見た目ではなく、その場の状況にそぐわない「行動」に注目することです。
【警戒すべき行動パターン】
- 不自然な滞在
-
子ども連れでもなく、運動や読書をするわけでもなく、ただ長時間にわたって子どもたちを観察している大人は要注意です。犯行の下見や機会をうかがっている可能性があります 。
- 不適切な関心
-
執拗に子どもたちの写真を撮ったり、特に理由もなく話しかけようとしたりする行動は危険な兆候です 。
- 状況との不一致
-
暑い日に厚着をしている(凶器を隠している可能性)、他の保護者との交流を不自然に避けるなど、その場の文脈から浮いた行動をとる人物には警戒が必要です 。
- 挙動不審な動き
-
頻繁に周囲をキョロキョロ見回す、他の大人と目が合うと逸らす、落ち着きがないといった行動は、何らかのやましい意図を隠しているサインかもしれません 。
【あなたの行動計画】
- 直感を信じる
「何となく嫌な感じがする」
「この人、ちょっとおかしいかも」
というあなたの直感は、多くの場合、無意識のうちに上記の様な行動の異常性を捉えています。その感覚を何よりも信じてください。
- 距離をとる
-
不審に感じたら、さりげなくお子様を連れて公園の別の場所に移動し、その人物との物理的な距離を確保しましょう。
- 存在を知らせる
-
相手としっかり目を合わせ、「私はあなたに気づいていますよ」というメッセージを送ります。これだけで犯行を思いとどまらせる効果があります。
- 周囲と連携する
-
近くにいる他の保護者に「あそこにいる方、少し気になりませんか?」と小声で相談してみましょう。一人で抱え込まず、周囲を味方につけることが重要です。
- 通報をためらわない
-
明らかに脅威を感じる行動や、しつこいつきまといなどがあれば、迷わず警察(110番)に通報してください。「勘違いだったら申し訳ない」と思う必要はありません。不審かどうかの最終判断は、プロである警察官に任せるべきです。
意外な落とし穴:親同士のトラブルを賢く回避・解決する方法
公園での親同士のトラブルは、単なる気まずい出来事ではありません。これは重大な「セキュリティ上の問題」です。
なぜなら、他の保護者と口論になっている間、あなたの意識は完全にその対立に集中し、最も重要な「我が子への監督」が疎かになるからです。
その数分間の隙に、子どもは道路に飛び出したり、遊具から転落したり、あるいは本当の不審者に声をかけられたりするかもしれないのです。
したがって、対立を回避し、速やかに沈静化させるスキルは、子どもの安全を守るための必須能力と言えます。
【トラブルの火種】
おもちゃの取り合い
一方の子が他方の子のおもちゃを奪ってしまう 。
乱暴な遊び
突き飛ばす、砂をかけるなど、遊び方が乱暴で他の子に危害が及ぶ 。
ルールの無視
遊具の順番を守らずに割り込む、危険な逆走をする 。
保護者の無関心
自分の子どもが問題行動を起こしているのに、スマートフォンに夢中になっている 。
専門家からのアドバイス
もし他の子がお子様のおもちゃを取ってしまったら、いきなりその親に文句を言うのではなく、まずその子自身に優しく話しかけます。
「そのスコップ、楽しそうだね。でもこれは〇〇ちゃんのだから、貸してって言えるかな?」
多くの場合、これで問題は解決し、親同士の対立に発展しません。
相手の親が近くにいるものの気づいていない場合、自分の子どもに、しかし相手の親にも聞こえるくらいの声で状況を説明します。
「あらら、あのお兄ちゃんにドンってされちゃったね。痛かったね。危ないから、あっちのブランコで遊ぼうか」
これは、直接的な非難を避けつつ、問題が起きていることを相手に伝える穏便な方法です。
状況が緊迫していたり、相手の親が攻撃的な態度を示したりした場合、あなたの最優先事項は「議論に勝つこと」や「正しさを証明すること」ではありません。
お子様を安全な場所へ移動させることです。
「さあ、もうお砂場は終わりにして、お家に帰ろうか」
その場を離れることは、負けではなく、賢明な「安全確保行動」です 。
もし自分の子が加害者になったら
これは親としての姿勢が問われる最も重要な瞬間です。即座に介入し、相手のお子様と保護者に心から謝罪してください。
そして、自分の子を少しその場から離し、なぜその行動がいけなかったのかを毅然と、しかし冷静に説明します。あなたのこの誠実な対応が、無用なトラブルを防ぎ、子どもにとっても重要な学びの機会となります 。
家庭で実践する防犯の基礎:教えるべきこと、備えるべきこと
外出時の対策はもちろん重要ですが、子どもの安全を守るための本当の土台は、日々の家庭生活の中にあります。
ここでは、ご家庭で実践できる防犯の基礎知識と、子どもに教えるべき護身のスキルについて解説します。
子どもに教えるべき護身術:「いかのおすし」とその先へ
多くの方がご存知の防犯標語「いかのおすし」は、子どもが覚えるべき基本の行動として非常に優れています 。
・いかない(知らない人についていかない)
・のらない(知らない人の車にのらない)
・おおごえでさけぶ(おおごえで助けを呼ぶ)
・すぐにげる(その場からすぐにげる)
・しらせる(近くの大人にしらせる)
しかし、専門家としては、この標語を覚えるだけでなく、より実践的なスキルを身につけることを強く推奨します。
- 効果的な叫び方
-
いざという時、子どもは恐怖で声が出なかったり、「キャー」という悲鳴しか上げられなかったりします。日頃から「助けて!」と具体的な言葉で叫ぶ練習をしましょう。言葉で叫ぶ方が、周囲の人も緊急事態だと認識しやすくなります 。
- 「腕の長さ」ルール
-
不審者との安全な距離を、親子で実際に体感してみましょう。
「大人の人が両手を広げたくらい離れていれば、すぐに捕まらないよ」
と、具体的な距離感(約2メートル)を教えることが重要です 。
- 「イヤです!」を言う練習
-
子どもは大人に対して「いいえ」と言うことに抵抗を感じるものです。親子でロールプレイングを行い
「イヤです!」「行きません!」
と、はっきりと断る練習を重ねましょう。これにより、いざという時にためらわずに行動できる自信が育ちます。
- 逃げることは「悪いこと」ではない
「失礼かな?」「間違っていたらどうしよう?」
といったためらいが、命取りになることがあります。
「怖い」「おかしい」と感じたら、相手に失礼だとか、丁寧に対応しなきゃなどと考える必要は一切ない、すぐに走って逃げていいのだと教え込んでください。「こども110番の家」など、駆け込める安全な場所を日頃から親子で確認しておくことも大切です 。
SNSの危険から子どもを守る:親が設定すべきルールと注意点
幼いお子様の場合、SNSの直接的な危険は、本人の利用よりもむしろ、「保護者から」、つまり子どもの写真や情報の共有に潜んでいます。
良かれと思って投稿した写真が、意図せず子どもの安全を脅かす情報源となり得るのです。
保護者の投稿に潜むリスク
個人情報の漏洩
写真のキャプションから子どもの名前やニックネーム、写真に写り込んだ制服や園の建物から所属が特定されることがあります 。
位置情報の漏洩
スマートフォンの位置情報(ジオタグ)がオンになっていると、写真が撮影された場所(自宅やよく行く公園など)が第三者に知られてしまいます。背景に写る特徴的な建物や看板からも場所は特定可能です 。
行動パターンの漏洩
「今日から〇〇教室!」「毎週火曜日はスイミング」といった投稿は、子どもの行動パターンを犯罪者に教えているのと同じです。
これらの断片的な情報を組み合わせることで、犯罪者は子どもの生活圏や行動スケジュールを正確に把握し、接触の機会をうかがうことができるのです 。
- スマートフォンのカメラ設定で、位置情報(ジオタグ)をオフにする。
- 自宅の表札やマンション名、学校名などが写り込んだ写真は投稿しない。
- SNSのプライバシー設定を必ず「友達のみ」などに限定し、不特定多数が閲覧できないようにする。
- 子どもの裸やそれに近い写真の投稿は、児童ポルノなどの犯罪に悪用される危険があるため、絶対に避ける。
お子様が成長し、自分でSNSを使い始めるようになったら、「ネット上で知り合った人には絶対に会わない」「個人情報を書き込まない」といったルールを、その危険性とともに繰り返し教える必要があります 。
我が家の防犯力向上:今日からできる住宅セキュリティ
子どもの安全の最後の砦は、やはり「家庭」です。
空き巣などの侵入犯罪は、子どもが一人で留守番をしている時間帯などを狙って行われることもあり、万が一犯人と鉢合わせすれば、非常に危険な事態に陥ります 。
専門的なセキュリティシステムを導入しなくても、今日から始められる対策は数多くあります。
- 侵入口を塞ぐ
-
侵入犯が最も多く利用する手口は、無施錠のドアや窓からの侵入です。こうした被害を防ぐためには、たとえ短時間の外出であっても、すべてのドアや窓をしっかりと施錠する習慣を身につけることが重要です。
特に玄関ドアや侵入されやすい窓には、「ワンドア・ツーロック(二重ロック)」を徹底しましょう。主錠に加えて補助錠を取り付けることで、侵入に要する時間を大幅に延ばすことができ、犯行を断念させる効果が期待できます。 - 光で威嚇する
-
犯罪者は人目を嫌います。玄関や庭の死角になりやすい場所に、人が近づくと点灯するセンサーライトを設置することは、非常に効果的な侵入抑止策です 。
- 音で知らせる
-
庭や建物の裏手など、人が通常歩かない場所に「防犯砂利」を敷きましょう。踏むと76デシベル以上(掃除機や電話のベルに相当)の大きな音が出るため、侵入者は極端に嫌がります 。
- 足場をなくす
-
2階への侵入の足場となるような、エアコンの室外機、ゴミ箱、物置、梯子などを、窓の下やベランダの近くに置かないようにしましょう 。
【人的な対策】
- 玄関での対応
-
モニター付きインターホンを設置し、子どもには「知らない人が来ても絶対にドアを開けない」というルールを徹底させましょう。
「宅配便だよ」
「警察だよ」
など、どんなことを言われても、保護者の許可なくドアを開けてはいけないと教えます
- 緊急時の計画
-
緊急連絡先を電話の近くに貼り出し、火事や地震、不審者が来た場合など、万が一の時にどう行動するかを親子で話し合い、練習しておくことが大切です。
おわりに:恐れるのではなく、備える。自信を持って子どもと過ごすために
ここまで、ベビーカーでのお出かけから公園での過ごし方、家庭での防犯対策まで、子育て中の皆様が直面する様々なシーンにおける安全確保の方法を具体的にお伝えしてきました。
お伝えしたかったのは、私たちの日常には確かに危険が潜んでいるという事実ですが、それ以上に、その危険は「正しい知識」と「日々の備え」によって、その多くが回避可能であるということです。
子どもの安全は、「状況認識」「準備」「習慣」という3つの要素の組み合わせによって成り立っています。
状況認識
ながらスマホをやめ、周囲に気を配ること。危険な公園のサインを見抜くこと。
準備
ベビーカーにロックをかけ、SNSのプライバシー設定を見直し、家の防犯対策を講じること。
習慣
子どもと防犯ルールを繰り返し確認し、危険な行動を注意し、安全な行動を褒めること。
これらの知識を身につける目的は、決して外出を恐れたり、他人を過度に疑ったりするためではありません。
むしろ、どこに注意すればよいかが明確になることで、漠然とした不安から解放され、自信を持って子どもとの貴重な時間を心から楽しむためです。
あなたはお子様にとって、最も信頼できる最高のボディーガードです。そして、その最強の武器は「知識」です。
本記事で得た知識を盾に、明日からのお子様との毎日が、より安全で、より豊かなものになることを心から願っています。






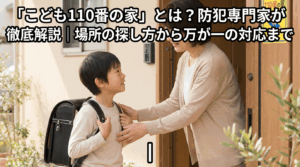
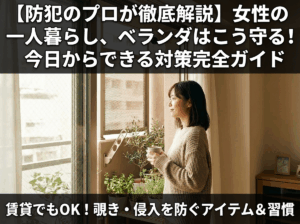

コメント